・どのくらい勉強する?合格まで必要な勉強時間は何時間?
・合格して気付いた勉強を始める前に知っておきたい5つのこと
・何を用意するべき?試験にも役立つ揃えておくべき勉強アイテムとは?
日商簿記2級合格を目指そうとしている人も多いですよね。
通信講座に申し込んだ方が合格の可能性は高い気がするけど、あまりお金をかけたくないな・・・と独学で挑戦される人も多いんじゃないでしょうか?
この記事では、日商簿記2級を独学で勉強する上で知っておいて損しない情報をまとめてみました。
私も独学で無事に2級(第159回の統一試験)合格しました。
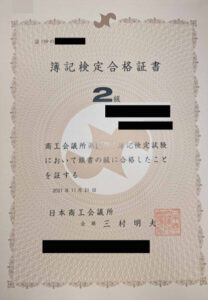
日商簿記2級も独学でもちゃんと合格できる資格です!

算数の時点で数字が苦手な私でも合格できたので自信を持って言えます(笑)
日商簿記2級の概要について
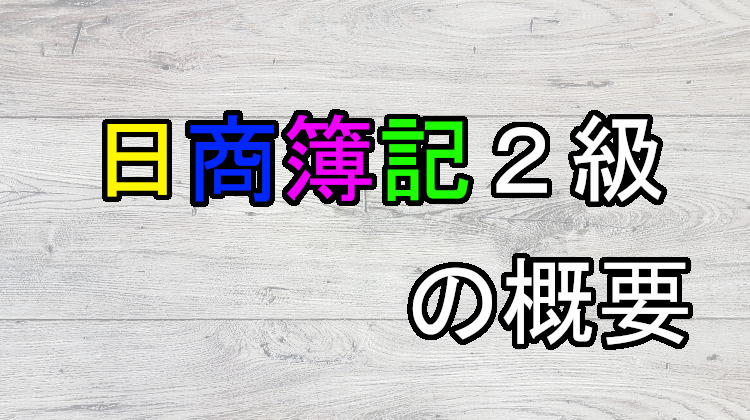
| 試験時期 | 毎年6月、11月、2月 |
| 合格基準 | 100点中70点以上 |
| 点数配分 | 商業簿記60点、工業簿記40点 |
| 試験時間 | 90分 |
| 受験要件 | 年齢学歴などの要件はない 3級未取得でも受験可能 |
日商簿記2級の統一試験は年3回あり、年齢条件などもなく学生さんでも社会人さんでも受験可能です。
また日商簿記3級の資格を持っていなくても2級や1級に挑戦できます。
※統一試験の受験方法はコチラで解説しています。
https://www.dove-ring.com/application-for-nissho-bookkeeping/
最近ではCBT方式の試験も導入されて、ますます受験しやすくなっています。
※CBT試験の受験方法はコチラで解説しています。
https://www.dove-ring.com/about-the-nissho-bookkeeping-cbtexam/
日商簿記2級合格に必要な勉強時間はどのくらい?

一般的に日商簿記2級に合格するには、200〜250時間程度必要と言われてます。
しかし、これは3級レベルの知識がある場合です。
簿記に触れたことがない方や、数字に苦手意識がある場合は更に勉強時間は必要になります。

私のように数字が苦手なのにいきなり2級挑戦する場合は、もっと時間が必要と考えるべきです!
独学だとスケジュールも自分次第ですし、教えてくれる人がいないので途中で躓くと先に進めなかったりと学習期間が長期化しがちなので、独学で短期間合格を目指すためには、
この3点は非常に重要です。
学習計画を立てる際の目安として、3級の資格者なら300時間、未経験者なら400時間を基準に設定するとよいと思います。
つまり、2級なら1日2時間勉強と仮定すると、
400時間÷2時間=100日
最低約4ヶ月は期間が必要と考えましょう。
簿記は勘定科目の暗記だけでなく計算に慣れることも必要ですし、直前で焦らないように学習期間の予定は余裕を持って設定しときましょう!
独学で日商簿記2級を効率的に勉強するために知っておいてほしいこと

ここからは、私がもっと早く知ってたら楽に勉強できたんじゃないかなーと感じていることを5点挙げていきます。

これから独学で2級の勉強をされる方の参考になれば幸いです
・簿記未経験者は3級の内容から始める
・初めに学習計画を丁寧に立てておく
・過去問や予想問題を90分で解いて試験慣れしておく
・工業簿記は左から右へ製品が流れるイメージを持つ
・YouTubeの簿記系チャンネルが活用できる
知っておいてほしい① 簿記未経験者は3級の内容から始める
当たり前だと思われるかもしれませんが、少なくとも私は3級は簿記の基本を学ぶもので、実践的なのは2級からなんて勝手に思い込んでおり、全く別物だと思ってました。

3級はテキストが1冊だけど、2級は2冊だし内容が全く違うなと思ってた時期が私にはあります
なので、勉強するにあたり2級のテキスト(問題集含め3冊)だけ買って勉強を始めてしまいました。
結論から言えば、3級のテキストはなくても合格できましたが、何度もネットで調べたりして非効率な学習だったうえに非常に苦労しました。
あえて言います、簿記未経験で三分法の時点で何のことかさっぱりな人は、3級のテキストも購入することをオススメします!!
知っておいてほしい② 初めに学習計画を丁寧に立てておく
学習計画なんて必要ある?って思う人も多いでしょうがとても重要なんです!
独学のデメリットは
ため、無計画に進めてくと学習期間が長期化しがちです。
学習計画を立てないと今日はいいやーってなってしまったり、1つの問題に固執して進めなくなることはありがちな話です。
学習計画をしっかり立てることによって、
などの効果が期待でき、短期間合格の可能性がグッと近づいてきます。
例えば私の場合、2月から勉強を始めて最初は何も考えずにダラダラやった結果、6月に受験した時は財務諸表がほぼ勉強できていない状態だったため普通に落ちました。

とは言っても自分の中では4ヶ月も簿記に向き合ってたんで、正直かなーりショックでした(笑)
今思えば、無駄な努力だったと思いますが、当時は結構ダメージがあり9月くらいまでやる気を無くしてました。
そこからなんとか自分を奮い立たせて、11月の試験に向け限られた時間で合格するために学習計画を決めるところから始めました。
11月の試験で合格するために残りの日数を洗い出し、どのくらい勉強時間が取れるのか?いつまでにどのあたりまで進めるのか?等を考え、学習計画を立てて勉強に取り組んだところ、効果は想像以上で以前よりサクサクと勉強が進み、また理解も早くなり無事合格することができました。
もちろん最初の4ヶ月で多少ながらも基礎があったからできたと思いますが、学習計画を立てていなければまた落ちていたんじゃないかと思います。
私自身、学習計画という比較対象があることで勉強の進み具合がグンとよくなったので、これから勉強を始めるかたは是非試してみてください。
知っておいてほしい③ 過去問や予想問題を90分で解いて試験慣れしておく
試験時間が90分って聞くと、割と時間に余裕ありそうと感じると思います。
ですが、簿記を受験してみるとわかるのですが全然足りません。
と時間を要するオンパレードで90分間なんてあっという間です。
簿記は、勘定科目を覚えることと正確な計算をすることどちらも大切なので、合格するには時間配分が重要なファクターになってきます。
適切な時間配分を身に付けるには、実戦形式に慣れておくことが最も簡単かつ効果的な方法です。
時間を計測しながら過去問や予想問題に挑戦しておくことで、自分なりの問題の進め方が掴めるようになります。
私も2回目の受験前に何回か挑戦したおかけで、本番では見直す余裕すら持つことができました。
知っておいてほしい④ 工業簿記は左から右へ製品が流れるイメージを持つ
工業簿記と商業簿記は、似ているようで考え方が結構違ってます。
慣れてくると工業簿記は得点源になるんですが、理解するまで結構時間が掛かりやすいです。
商業簿記との大きな違いは、工業簿記は製品の工程ごとに仕訳をしていくところです。
納品→原材料→仕掛品→製品→出荷
のような感じで、借方に入れて貸方で出すみたいなイメージができるかが大切だと思います。
工業簿記は、イメージさえできれば理解が早まりますし必要な図も迷わずに描けるようになるのでうっかりミスさえ気を付ければ満点も可能な分野だと感じます。

仮に満点なら40点、となると商業簿記は30点あればいいので精神的にだいぶ楽になっちゃう!
知っておいてほしい⑤ YouTubeの簿記系チャンネルが活用できる
個人的には、これが最も早く知っておきたかったナンバーワンです(笑)
ぶっちゃけYouTubeはエンタメ系のコンテンツという認識しかなく、まさか資格勉強にも使えるなんて夢にも思わなかったんですよねぇ・・・(遠い目)
ただでさえ3級の知識がないまま2級に挑戦してたため、わからない部分を毎回ネット調べながら勉強してたんですが、これが本当にストレスでした。
YouTubeで勉強できることを知ってからはそんなストレスがかなり軽減され、楽しく覚えることができました。
などなど、いいことずくめです!
もちろんテキストの方が優れている部分もありますので、YouTubeだけでは苦労しますがどちらも上手く使っていいとこどりすれば、合格に手が届きやすくなります。
私はYouTubeで勉強できることを知ったのは1回落ちてからなので、最初に知っていれば6月に合格できたんじゃないかとさえ思ってしまいます。
(多分、それでもダラダラ勉強して落ちてたとも思いますが(笑))
個人的にオススメのチャンネルは、ふくしままさゆき様のチャンネルです。
https://www.youtube.com/channel/UCGDec349YIziUytZzc3d7Yg
3級と2級の出題内容をものすごく丁寧に解説しておられるので、見るだけで効果があると思います!
他にも様々なチャンネルがありますので、一度検索してみて下さい!
日商簿記の勉強に必要なアイテムについて
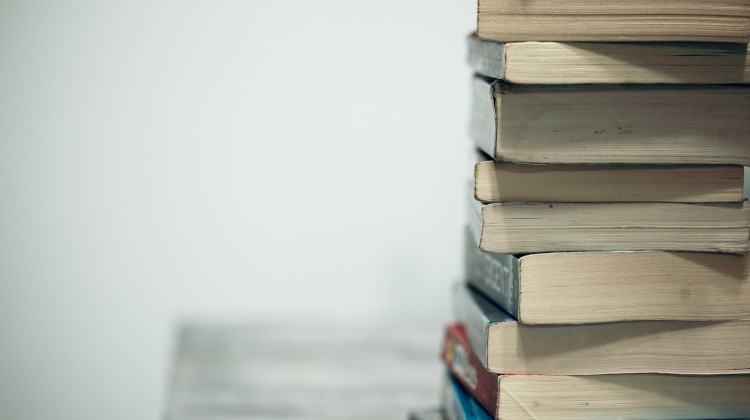
簿記を勉強を始める前に揃えておきたアイテムを紹介していきます。
必要なアイテム① テキスト
テキスト選びはある意味、一番重要です。
簿記は人気のある資格なので、様々なテキストが存在するためどれがいいんだろうとちょっと贅沢な悩みを抱えがちです(笑)
正直どのテキストでもいいと思いますし、強いて言うなら「テキストは本屋さんで買いましょう」です。
なぜなら
・自分が気に入るか
この2点は抑えておくべきだからです。
古いテキストだと、現在の出題内容にそぐわなかったり、文字ばっかりで眠気を誘う内容だとやる気が続かないなんてことになりかねません。
テキストはネットでも購入できますが、後悔しなくて済むのは本屋さん購入する方法だと思います。
一応、私が購入したテキストはコチラです。
商業簿記と工業簿記、過去問&予想問題集の3つあります。
とは言えこのシリーズは2020年版なので、購入するならこのシリーズじゃなくて2022年の試験に対応しているものを購入して下さいね。
面倒に感じるかもしれませんが、テキストといい出会いをするために直接確認しちゃいましょう♪

ちなみにですが電子書籍版のが安いですが、紙の書籍の方が断然使いやすいです!
必要なアイテム② 電卓
電卓もある程度の製品を用意しましょう。
高度な計算機能のついた高級電卓は、試験で持ち込み不可だったりするので高いものを購入する必要はないですが、個人的には文具店で1,000円前後で販売しているものがオススメです。

カシオの電卓が一番使いやすいと思います
何故、電卓について書いたかと言うと、最初100均で300円(税抜)の電卓を買ったんですが、ボタンが押しにくく、しかも反応も悪くて本当にストレスマシマシでした。
結局、文具店で買いなおしたので300円は無駄な出費でしたね。
ちなみに、私はこの電卓(ピンク)で試験に挑みました(笑)
派手目な色の方が失くしにくいんじゃないかって思います。
必要なアイテム③ 鉛筆と消しゴム
鉛筆と消しゴムは試験で使用するため、用意する必要があります。
これらの筆記具は、社会人になってある程度年数が経つとあまり使う機会が無くなりがちです。
特に消しゴムは劣化してると消しづらくなるので、古いようなら買い替えましょう。
必要なアイテム④ ノート(ルーズリーフ)
ノートもルーズリーフとリングファイルの組み合わせがオススメです。
勉強していると、後になってページの追加や差し替えをしたくなることも多いと思います。
そんな場合に、簡単に入れ替えができるルーズリーフだと効率的に勉強できます。
些細なことかもしれませんが、こういうストレスを取り除くことも勉強には大切だと感じています。
大きさはB5が持ち運びには便利です。
リングファイルも100均のものより文具店で売ってるヤツのほうがしっかりしていて長く使えると思います。
その他のあると便利なアイテム
3色ボールペン
重要だと感じるものは赤色、苦手に感じるものは青色のように色分けしたり、テキストに書き込んでおくと見直すときにパッと一目でわかるので勉強効率が上がります。
修正テープ
計算を間違ったときなどにピッと修正できるので、あるととても重宝します。
私のように、書き間違いが多くなりがちな人ほど用意しておいて損はないです。
蛍光ペン
テキストの重要箇所へマーカするときに使うため、1色あると便利です。
何色も用意しても見辛くなるだけなので、多くても2色あれば十分です。
テキストは汚してなんぼだと思いますのでどんどん使っていきましょう(笑)

私は、汚したくないと思ってしまいマーカーはほとんど入れなかったんですけど・・・(駄
付箋
テキストやノートのよく見返すことになりそうなページや躓きやすい箇所に貼ったりすることで、快適に勉強ができます。
地味に感じるかもしれませんがストレスが軽減するので、付箋は用意しておくべきアイテムです。
日商簿記2級は決して手の届かない資格ではありません!

日商簿記を勉強する上で覚えておいてほしいことと、勉強時間の目安やアイテムを紹介しました。
私自身、数字は小中学生の時点で苦手意識があるため今でもかなり苦手ですが、そんな状態でも頑張れば日商簿記2級も合格は十分可能だと自分で実体験できました。
簿記は、お金の流れを掴むことのできる学問で、仕事だけでなく社会で生きていくうえで非常に重要な知識だと思います。
せっかく勉強するなら、試験合格するために勉強するのではなく自分の身となり肉となるように丁寧に学んで覚えていきましょう。
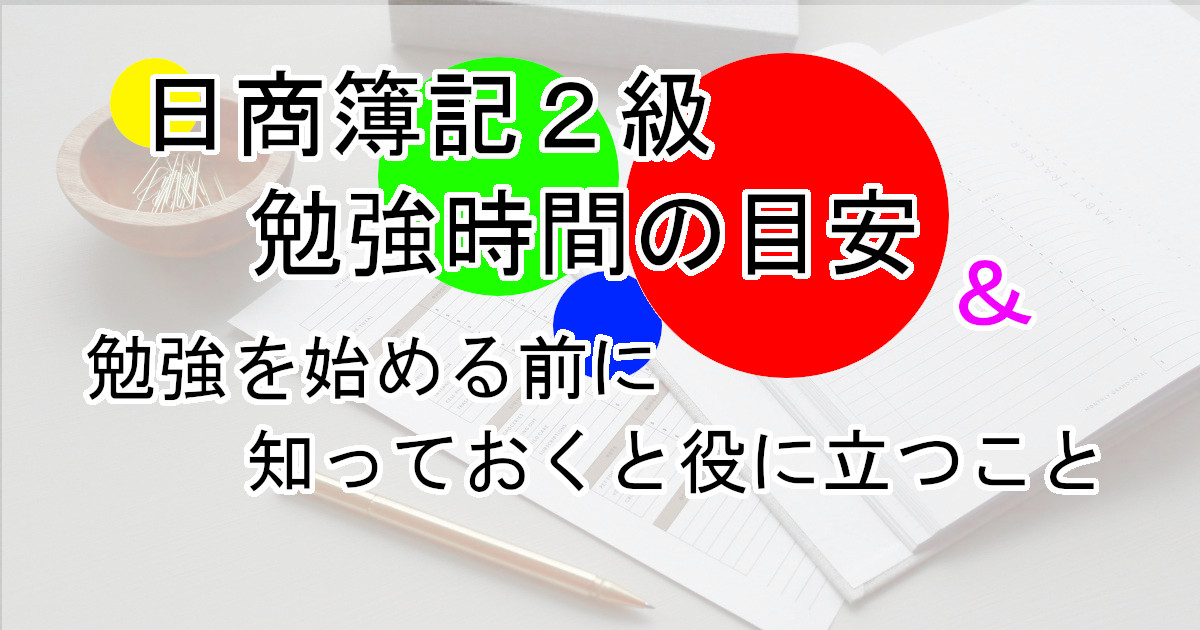

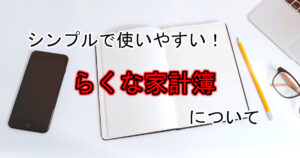
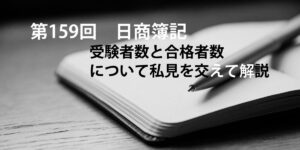
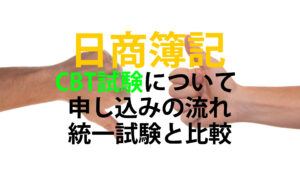
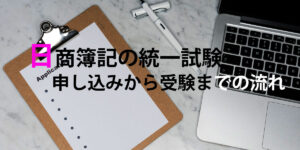
(実際に計って勉強したわけではないのでかなりアバウトですがこのくらいはかかってます)